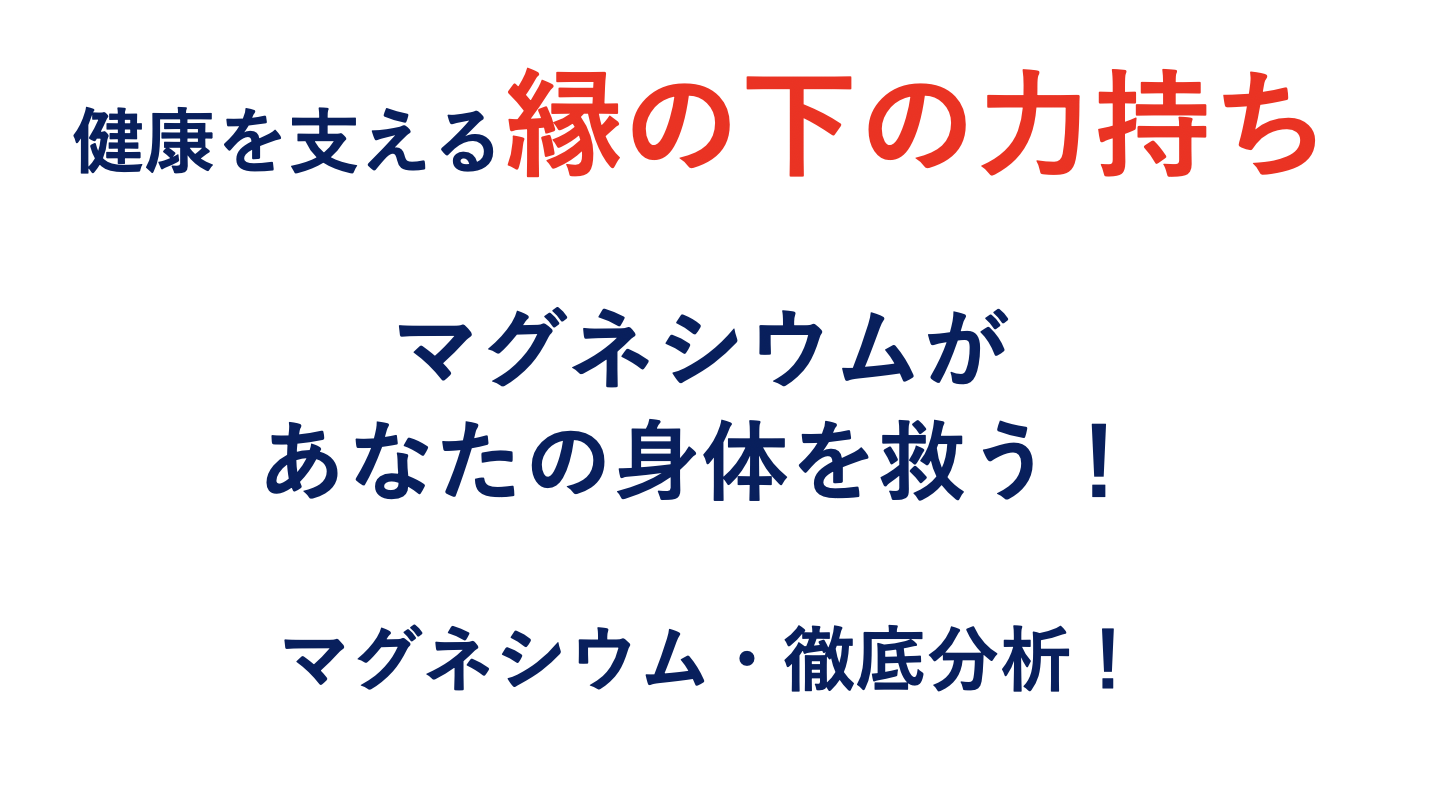『マグネシウム』は体内で300以上の酵素反応に関与し、多くの生理機能を支える必須ミネラルです。
今回は、
健康を支える縁の下の力持ち
マグネシウムがあなたの身体を救う! 『マグネシウム』徹底分析!
と題して、マグネシウムの働きや効果効能について解説したいと思います。
【マグネシウム】の働き・効果効能

◉筋肉の収縮と弛緩を調整
◉神経の伝達をサポート
◉心臓のリズムを安定化
不整脈の予防や心血管の健康維持に関与しています。
◉エネルギー代謝の促進
ATPの生成に必要不可欠とされています。
◉骨の形成を助ける
カルシウムとともに骨を強くする働きがあります。
◉血圧の調整
高血圧の予防・改善に役立つ可能性があります。
◉糖代謝の調整
インスリンの働きを助け、糖尿病予防に貢献します。
◉頭痛や片頭痛の軽減
特に片頭痛の発作頻度や重症度を抑えます。
◉PMS(月経前症候群)の症状軽減
◉不眠の改善
神経の興奮を抑え、リラックス効果を促進します。
◉うつ症状の緩和
セロトニンの生成に関与し、精神安定に寄与します。
◉消化酵素の活性化
◉便秘の改善
腸の動きを活発にし、便通を促します。
◉炎症の抑制
慢性炎症の抑制による生活習慣病予防が期待されています。
◉免疫機能のサポート
免疫細胞の正常な働きを支えます。
◉細胞の安定性を維持
◉DNAやRNAの合成に関与
細胞分裂や再生に不可欠です。
◉血栓の予防
血液の流れを滑らかに保ち、心血管疾患のリスクを低減します。
◉酸化ストレスの軽減
抗酸化作用により細胞老化を抑えます。
◉肝機能のサポート
【マグネシウム不足】による症状と病気のリスク
◉筋肉関連の症状
・筋肉のけいれん、痙縮(けいしゅく)
・筋力低下
・まぶたのピクピク
◉神経・精神症状
・不安感
・うつ症状
・イライラ
・集中力の低下・不眠
◉心臓・血管系
・不整脈(心拍の乱れ)
・高血圧
・冠動脈疾患や心筋梗塞のリスク上昇
◉代謝・内分泌系
・2型糖尿病のリスク上昇(インスリンの感受性が低下するため)
・骨粗しょう症(カルシウム代謝に関与するため)
◉その他
・偏頭痛(マグネシウムの低下が関連)
・慢性疲労
・PMS(月経前症候群)の悪化
・便秘(マグネシウムは腸の動きを助けます)など
◉マグネシウム欠乏の原因例
・栄養不足(偏った食事、ダイエット)
・アルコールの過剰摂取
・利尿薬や制酸薬の長期使用
・慢性的な下痢や吸収障害(例:クローン病)
・ 糖尿病(尿からの排泄増加)など
マグネシウムを多く含む食品の例
◉種実類・ナッツ類
・アーモンド(100gあたり 約270mg)
・カシューナッツ(100gあたり 約290mg)
・ヒマワリの種(100gあたり 約325mg)
・ごま(100gあたり 約350mg)
・クルミ
・落花生
・そら豆
◉海藻類
・わかめ(乾燥)(100gあたり 約1,000mg)
・ひじき(乾燥)(100gあたり 約640mg)
◉大豆製品
・豆腐(絹ごし 100gあたり 約40mg)
・納豆(1パック 約50mg)
・おから(100gあたり 約81mg)
◉魚介類
・しらす干し(100gあたり 約120mg)
・帆立
・かに
・鮭
・あさり(100gあたり 約100mg)
◉穀類・雑穀類
・玄米(100gあたり 約110mg)
・オートミール(100gあたり 約100mg)
・そば(乾麺100gあたり 約120mg)
◉野菜・果物
・ほうれん草(ゆで100gあたり 約40mg)
・小松菜(ゆで100gあたり 約50mg)
・ブロッコリー
・バナナ(1本 約30mg)
・アボカド(1個 約40mg)
など
食品として摂取したマグネシウムは主に小腸から吸収され、吸収率は40%〜60%程度と推定されます。
経皮吸収も可能なマグネシウム
◉にがりの活用
食品からの摂取はもちろん、『にがり』を料理に利用することも有効です。
◉経皮吸収でマグネシウムを摂取する方法
皮膚から直接吸収することで、経口摂取とは異なる効果も期待できます。
・筋肉の緊張や痛みを和らげる
・肌の炎症を鎮める
・皮膚のカサつきを改善する
・皮膚のバリア機能を高める
他、
・胃腸への負担が少ない(消化器官への負担が少ない)場合がある
・経口摂取よりも経皮吸収の方が効率的に吸収されることがある
などの効果が期待できます。
◉エプソムソルト
◉マグネシウムクリーム
の活用も有効です。
■マグネシウムを含むおすすめサプリメント
マグネカルD
大切なミネラルを毎日コツコツ補給
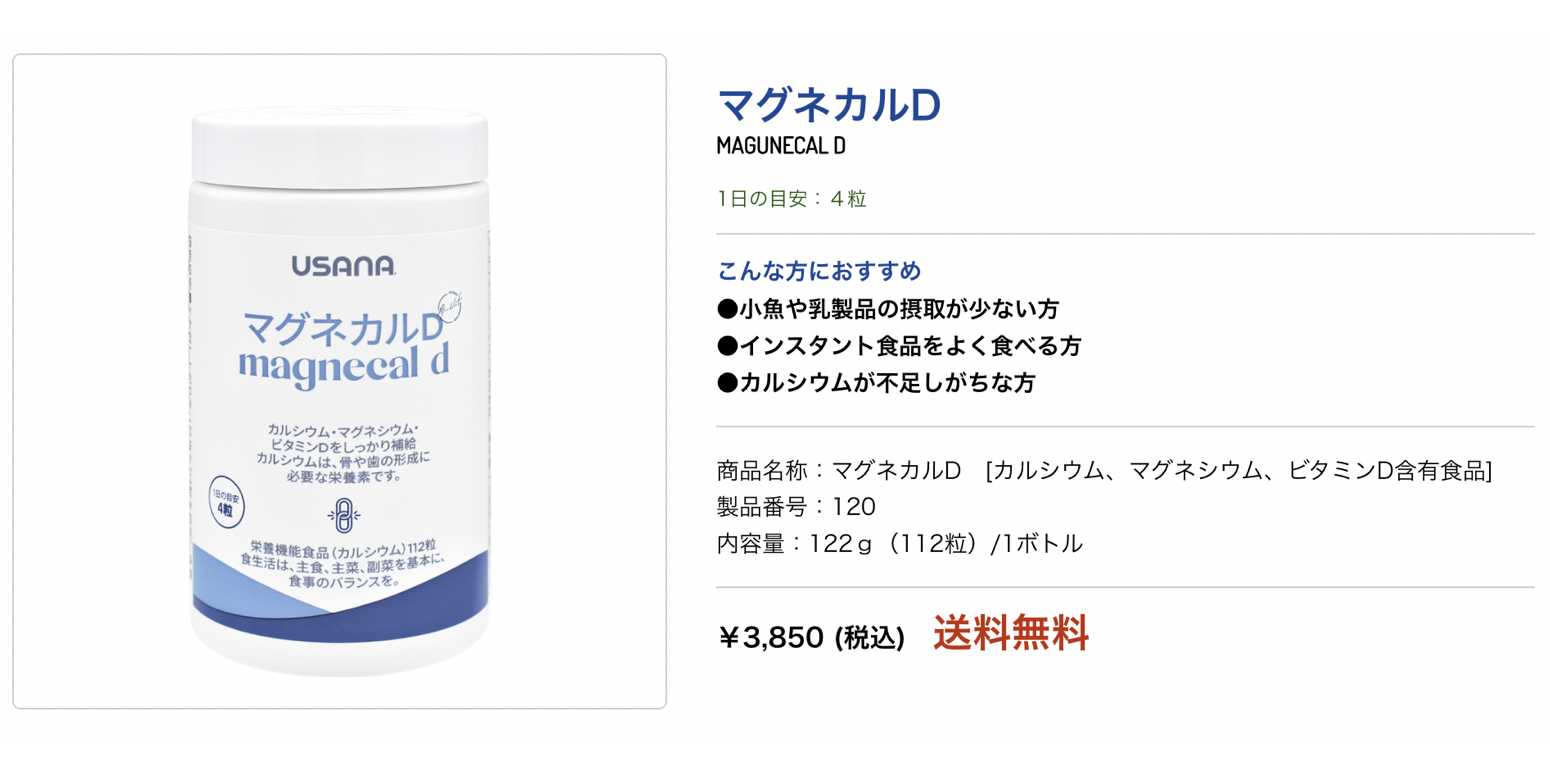
マグネカルDはここが違う
カルシウムとマグネシウムの比率が1:1
人の骨の構成に近く、吸収されやすいミルクカルシウムを使用
カルシウムの吸収を高めるビタミンDを配合
マグネカルDで、大切なミネラルを毎日コツコツ補給
マグネカルDについて、詳しくはコチラをご覧ください♪
↓↓↓↓↓
まとめ
必要量は年齢・性別・健康状態によって異なります。
健康を支える縁の下の力持ち『マグネシウム』
ぜひこれを機会に日々の生活に『マグネシウム』を取り入れてみてください。